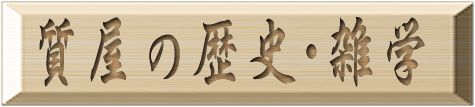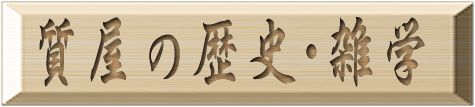質屋700年の歴史と申しますが、そのルーツは遣唐使の時代に遡るとも言われますが、一般的には貨幣経済が発達してきた鎌倉時代とされています。物々交換から貨幣経済に移行してくると、どうしても、お金がある時と無い時が出来るのは世の常です。それゆえ、貨幣経済の発達とともに、質屋の重要性も増してくるのですが、歴史の授業で習ったとおり、幾度かの戦乱の世を経て、貨幣経済が全国津々浦々まで浸透した江戸中期、元禄時代に今の形に落ち着いたものと思われます。落語や時代劇でも質屋の存在は重要ですが、歴史上有数の大商人三井財閥の創始者、三井八郎左右衛門高利も江戸に出て越後屋呉服店(現在の三越)を開く前は質屋をやっていたように、地方の有力者や名主が領民に担保を取って一時的に金を貸し付ける事は想像に難くない事と思います。、
質物につきましては、昭和40年代ぐらいまでは、一部で貴金属・宝石類、美術骨董品などのお宝もありましたが、呉服・洋服など衣類や、ふとん、ナベ、釜など生活生活用具一般を取り扱っていました。その後テレビ、ラジカセ、VTRなど電化製品の普及とともに、そうした電化製品、また国民生活の向上とともに、高級腕時計やルイ・ヴィトン、シャネルなどのブランドバッグ・財布・アクセサリーが加わり、その他、趣味性の高いカメラやパソコン、オーディオ機器、プレイステーションなどゲーム機まで多岐にわたっております。
ただし、国民生活が豊かになり、使い捨てが一般的になると、中古品でも価値があるものが少なくなってきました。貴金属類などは一皮剥いてしまえば、あるいは、溶かして作り変えてしまえばまた新品に戻ります。傷がつきにくいダイヤモンドは新品と同じ値段で取引きされます。しかし、それ以外の物は中古になっても他人が欲しがる理由が必要です。例えば、この世に一点しかない希少品であるとか、新品なら手が出せないような高額商品であるとかです。また、流行商品のようにその流行が終わってしまえば、誰も欲しくなくなるというのでは、価値も無くなってしまいます。近年ナイキのエアー・マックスやたまごっち、Gショックなどのブームを経験してきた若い方々なら体験済みの事と思います。以前、質屋でも主流だった洋服は既製服に押され、質草としての価値はほとんど無くなり、着物も毎年のように流行を追う柄が採用されたために、質草としては扱いにくくなってきました。
|
|
|
|
明治39年当時の台帳の一部抜粋 |
|
| 女 帯 |
1本 |
60銭 |
|
モミ種 |
2カン |
2円 |
| 布 団 |
1枚 |
40銭 |
モチ白 |
9升分 |
1円30銭 |
| コーモリ傘 |
10本 |
1円10銭5厘 |
大麦 |
2斗6升 |
1円40銭 |
| 木綿半天、子供羽織 |
90銭 |
印半天 |
|
35銭 |
| 掛け軸 |
1本 |
70銭 |
ナタ、キセル、 |
各1本 |
35銭 |
| 白天幕 |
|
60銭 |
荷車 |
1台 |
4円 |
| 子供袷 |
|
10銭 |
羽二重 |
|
15円 |
| 掛け時計 |
|
1円 |
モチ米 |
2斗2升 |
2円50銭 |
| 縮緬3尺 |
1本 |
2円80銭 |
ザル入りモミ種 |
40銭 |
|
|
|
|
|
|
|
| 営業時間 |
|
4月〜9月 |
午前6時〜午後5時迄 |
|
|
|
10月〜3月 |
午前7時〜午後4時迄 |
|
| 利 息 |
|
貸付金の利子の割合は25銭以下は1ヶ月1銭 |
|
|
1円以下 |
|
1ヶ月 100分の4以内 |
|
|
5円以下 |
|
1ヶ月 100分の3以内 |
|
|
10円以下 |
|
1ヶ月 100分の2.5 |
| 流質期限 |
|
マユ穀物等は3ヶ月、器物・衣類は6ヶ月 |
| 注意事項 |
|
火事、盗難は両損の事。ねずみ、虫喰、カビ、
変色その他は置主のき損、非常の場合は出物
は頂きまじく候 |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|